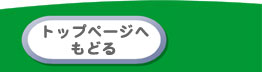序にかえて
1 合併の背景と必要性
(1) 合併をとりまく社会的経済的動向
少子高齢社会の進展、産業の空洞化や就業構造の変化などによる地域経済の低迷、資源リサイクルや地球温暖化といった住民の環境への意識の高まりなど、行政ニーズが多様化、高度化する社会経済情勢の中で、平成12年4月から地方分権一括法が施行されました。
地方分権型社会においては自治体の自主性が尊重され、住民に最も身近な地方公共団体である市町村には、これまで以上に幅広い分野で大きな役割を果たすことが求められています。
その一方で、景気の長期低迷等により、国、地方とも財政は厳しい状況にあり、税収の伸び悩み、財政の硬直化を招いています。財政の健全化を図るため、国において、地方交付税制度等地方財政制度の見直しが進められている中、地方交付税の依存度が高い本地域においては、自主財源の確保と、より一層の効率的な行財政運営を行っていく必要があります。
(2) 合併の必要性
①〝鹿角はひとつ〟
鹿角市と小坂町は、古くから尾去沢鉱山、小坂鉱山などが開鉱し、共に鉱山のまちとして発展してきました。
しかしながら、その後の急激な円高や鉱石の枯渇等の影響によって、相次いで閉山、縮小せざるを得ない状況に陥り、いまだこの地域の経済に大きな打撃を与えています。
そのため、鉱山跡地を観光資源として活用したマインランド尾去沢、鉱業技術を活かした資源リサイクルやゼロエミッションを目指すエコタウン事業など、地域資源を活かして地域を活性化するためのさまざまなプロジェクトを推進していますが、両市町ともに人口の流出はやまず人口減少や少子高齢化が進んでいる状況にあります。
合併後においては、地域経済の基盤づくりが最大の課題であると考えられますが、このような極めて困難な課題に対応していくためには、共通した課題をもつ鹿角市と小坂町が一体となり、相互に連携し合って、共に地域を活性化するためのプログラムを総合的に策定し、同じ圏域に位置する地域として総力をあげ、着実に施策を推進していく必要があります。
また、新市においては、特にまちづくりのための組織を強化し、企画及び計画力のある自ら行動する人材の育成に努め、地域住民の協働によるまちづくりを進めていくことが求められています。
② 生活圏の拡大と住民ニーズの多様化・高度化への対応
鹿角地域1市1町は、比較的類似した自然条件のもとで、鉱業を基幹産業として発展してきた地域であり、豊かな自然の恵みを財産として農業や林業などの第一次産業を中核とし、暮らしを営み風土を育んできた地域でもあります。
また、高速交通網の整備に伴い、住民の行動エリアが飛躍的に拡大し、人々の日常生活や経済活動は各市町の境界を越え、中でも通勤・通学をはじめ、買物などの生活行動は、強い結びつきを持ち、相互に依存し合いながら一体的な生活圏を形成しています。すでに消防や救急、ごみなどの衛生処理、斎場などは鹿角広域行政組合を組織し、広域的な連携が図られています。
加えて、住民が求める行政へのニーズも、多様化・高度化し続けており、また環境問題や高度情報化、生活圏の拡大などに伴い、従来の市町の範囲を超えた広域的な対応が求められています。
このような状況にあって、鹿角地域は広域的観点に立った大きなスケールで、かつ、地域の個性を活かしながら、より一体的なまちづくりを計画的・効率的に進め、住民が求める多様化・高度化するニーズに対応していく必要があります。
③ 少子高齢化の進展に伴う社会構造の変化への対応
鹿角地域においても少子高齢化の進展が顕著であり、高齢化の進展と少子化による急激な社会構造の変化は、人口の減少による地域活力の減退を招き、市町の行財政能力の低下へつながることが懸念されます。
また、高齢化の進展は、保健、医療、福祉等における行財政需要のさらなる増加をもたらすものと予想されます。
このような状況に対応するため、人的・財政的な基盤の整備・充実が求められていますが、各市町単独での対応には限界があり、地域一丸となった少子高齢化対策への取り組みが求められています。
④ 地方分権の推進と行財政基盤の強化
最も住民に身近な基礎的自治体である市町村は、地方分権の担い手として「自己決定・自己責任」の原則のもとに、変貌しつづける社会経済情勢に対応し、地域住民の福祉向上のため、様々なサービスの提供を行っていかなければなりません。
そのためには、適切な要員確保や専門的人材の育成を図るなど、分権時代にふさわしい体制を整えていく必要があります。
また、少子高齢化という社会構造を背景に、これまでのような行政サービスの水準を維持し、さらに向上させていくためには、徹底した行財政改革による効率的な行政運営の確立を図ることが必要です。
地方分権を担い、地域の持続的な発展を図り、主体的・自立的な行政運営を可能にするには、効率的な行政運営と行財政基盤の強化が重要となります。
2 将来構想の策定趣旨
この将来構想は、鹿角地域1市1町の新市建設計画を策定するために、新市の将来像やまちづくりの基本的な方向など、新市の将来の姿を明らかにすることを目的として策定するものです。
3 将来構想の構成
この将来構想は、現状分析、新市の将来像、まちづくりの基本方向、戦略的なプロジェクト、財政シミュレーションなどによって構成されます。
4 将来構想の計画期間
この将来構想の計画期間は、平成17年4月から平成27年3月までの10ヵ年とします。 |